この記事は卒塾生である沼邊 国太(ぬまべ くにた)くんが東京大学1年生の時に行ったインタビューをもとに作成されています。
墨田区と足立区で30年続くそろばん教室
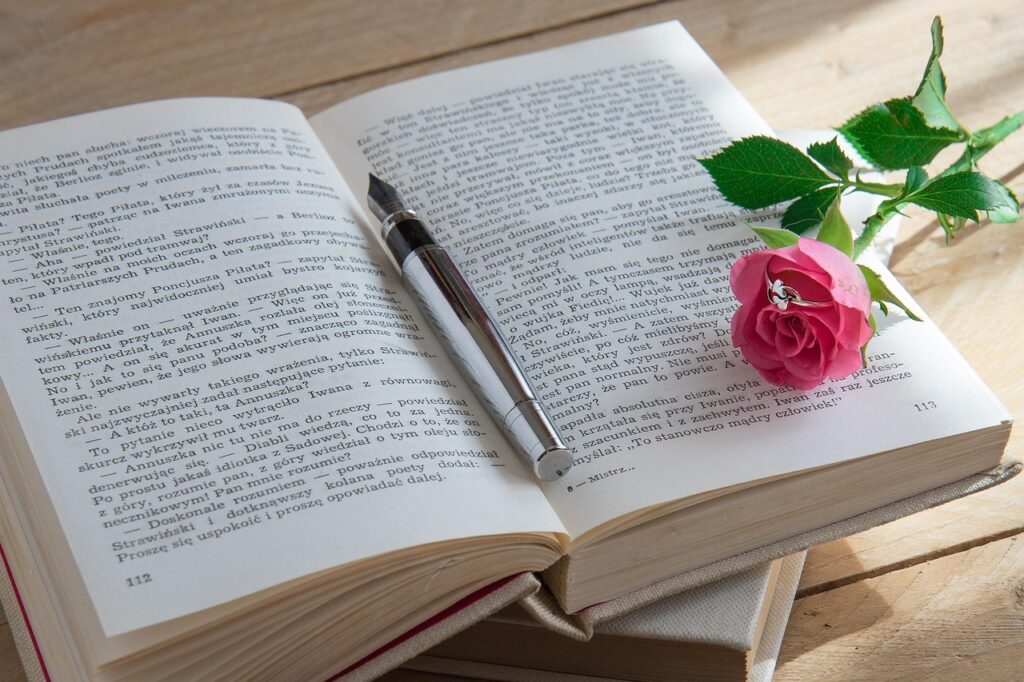
足立区で生まれて
僕は今回、長年お世話になったそろばん塾の山崎先生にライフストーリーを聞き取ることにした。現在先生は東京の墨田区と足立区の2カ所でそろばん塾を経営している。
先生は足立区で生まれ、今もそこで暮らしている。先生の祖父はおもちゃ工場をやっており、ブリキの玩具を作っていてとても繁盛していた。
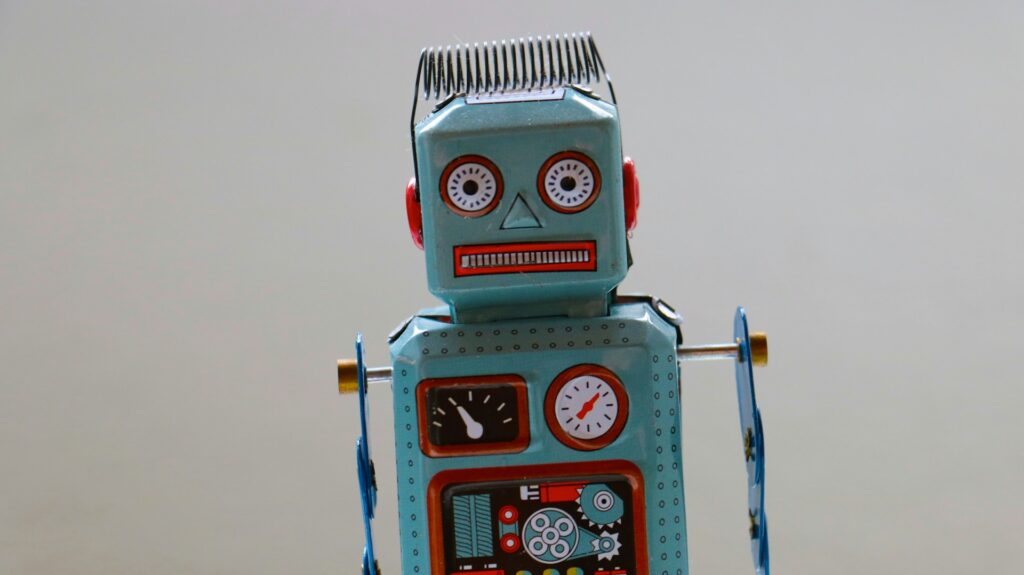
昔は集団就職と言って、17か18歳になると集団で田舎から東京に出てきて働くのですよ、祖父の工場には何百人もの女工さんがいて、その人たちを寮に入れて、働いてもらって、寮でご飯を食べたりしていましたね
先生の祖父は玩具協会の長で、亡くなった後、工場の人たちがお金を出し合い、功績を讃えるために銅像を作った。今でも先生の家の前には大きな銅像が建っている。
しかし先生の父親が仕事を継いで昭和43年に工場は潰れてしまった。主な原因はプラスチックなどの新しくて安価な素材が登場してきたからだ。
そろばんの先生になろうと思ったのは

先生がおもちゃと関係のないそろばん塾の先生になろうと思ったきっかけは、自分が習っていたそろばん塾の先生の影響だそうだ。
わたしは、中学校ぐらいの頃から、先生が忙しい時に生徒の採点をしたり、先生がいない時に読み上げ算(数字を読み上げること)をしたりするのを任されていてね、授業が終わると先生が一緒にご飯に連れて行ってくれたりしたのが嬉しくてね。だんだんそろばんの先生というかそろばんに惹かれていったのだろうね
親の反対を押し切りそろばんの先生に
しかし、先生の親は反対した。
「早く就職して嫁に行ってOLとかになってちゃんと子供を育てなさい」
当時、そろばんの先生は男の人がほとんどで、女性がやる職業ではなかった。しかし、先生は親の意見に反対し就職せずに、自分が通っていたそろばん塾を週1回手伝いし、また墨田区にもともとあったそろばん塾を引き継ぎ、週3回授業をしていた。それ以外の日は、先生は父親を介護していた。
父親が亡くなり生活もだいぶ落ち着いたところで、「自分で一から始めるそろばん塾を始めたい」と思うようになり、自分の実家をそろばん塾にして、新たに塾を始めることにした。
恩師の存在
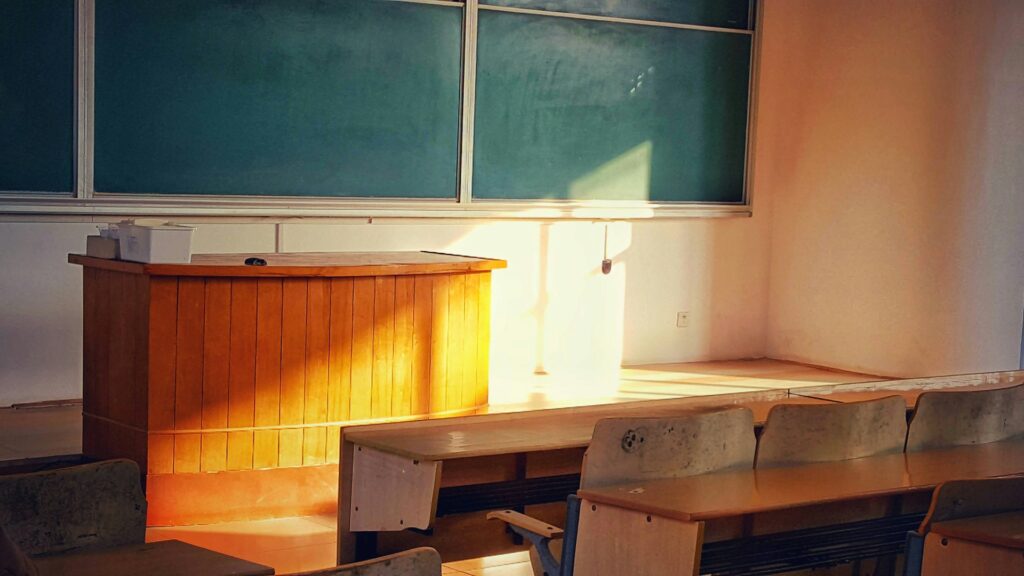
現在まで、墨田区のそろばん塾は35年、足立区の塾は24年(※取材当時)教えてきた。教えの根底にあったのは小学校5年生の時に担任だった先生と、自分がそろばん塾で教わっていた先生だという。
小学校の5年生の時の担任の先生は、ただ数学を教えるんじゃなくて、生徒が楽しんで勉強を仕向けるような工夫をしていたのね。休み時間に一緒に遊んだりして、生徒との関係もすごく大切にしていてね、あと、卒業式の時には生徒一人一人に色紙と手紙を渡してくれて、今でも取ってあるけれども(笑)
その担任の先生の影響を受け、今のそろばん塾でも課題が終わったらお菓子をあげたり、誕生日の月にはケーキを贈ったり、授業に来て貯めたポイントでおもちゃをゲットできたりなど、様々な工夫をしている。
そろばんを通して学んでほしいこと~山崎先生の想い~
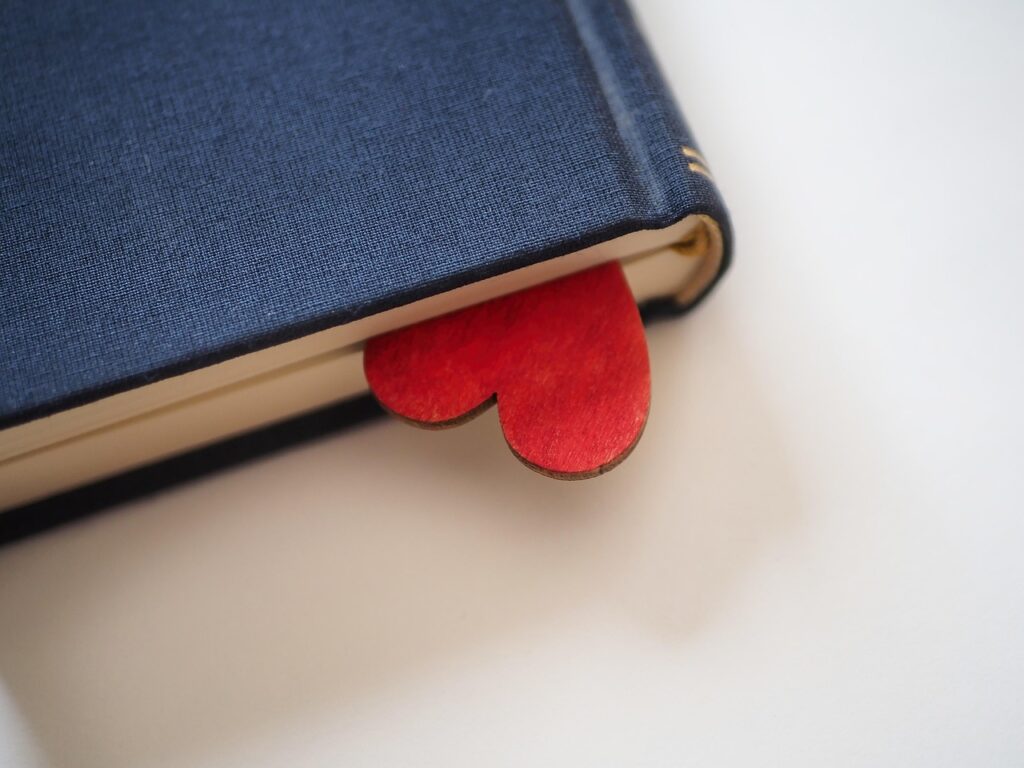
先生はそろばんも上達してほしいがそれ以上に人間的な成長、人間関係を学ぶ場になればと言う。
もちろん級を上げるのも重要だけど、人間的な成長をする方がもっと大事なんじゃないかな。特に最近は、近所のおじさんおばさんが叱ったりする機会も減り、核家族がほとんどで、共働きの家庭が多く、親が子供に目をかけられる時間が少なくなってきている中で、子供が人間関係を学ぶ機会が減っている。
だから、せめてうちのそろばん塾では人間関係やコミュニケーションの面を教育していきたい。夏に日帰りで旅行に行き、冬にスキーに行くのも、そういう教育の一環なのね。最近はこういう旅行とかで怪我とか事件が起きたりすると面倒だからって言って辞めてしまうそろばん塾も多いけどね
そろばんを教える内容は塾によってほとんど変わらない。どうせ教えるのだったら他の面でも教えたいと思い、他国のそろばん塾と国際交流をしたりする大掛かりな行事も行い、生徒の視野を広げる工夫をしている。
このような国際交流を開催するのはお金も非常にかかり大変だという。しかし、生徒のためを思えばいい事だし、何より生徒が人間的に成長してくれるのが嬉しいと、先生は話す。
もちろん利益を考えなくちゃいけないけれど、利益を考えてばかりいては普通のそろばん塾になってしまう。生徒の成長を第一に考えるっていうのが一番重要だよ
自分のそろばんの先生がそう考え、指導してきたのが、今でも自分の指導の根本にあるという。このような一貫したモットーで塾をしてきたが、昔と比べると生徒は少なくなっている。
これまでも、そしてこれからも
わたしの先生は、『生徒が少なくなるから生徒の人数は数えるな』って言っていたけど笑
最初は40人くらいから始めたけど、最盛期には150人ぐらいにはなっていたね。昔は銀行に勤める人、デパートに勤める人はある程度そろばんができなきゃ働けなかったけど、今は電卓とかパソコンとかができてきてあまり算盤の需要がなくなってきているからね…
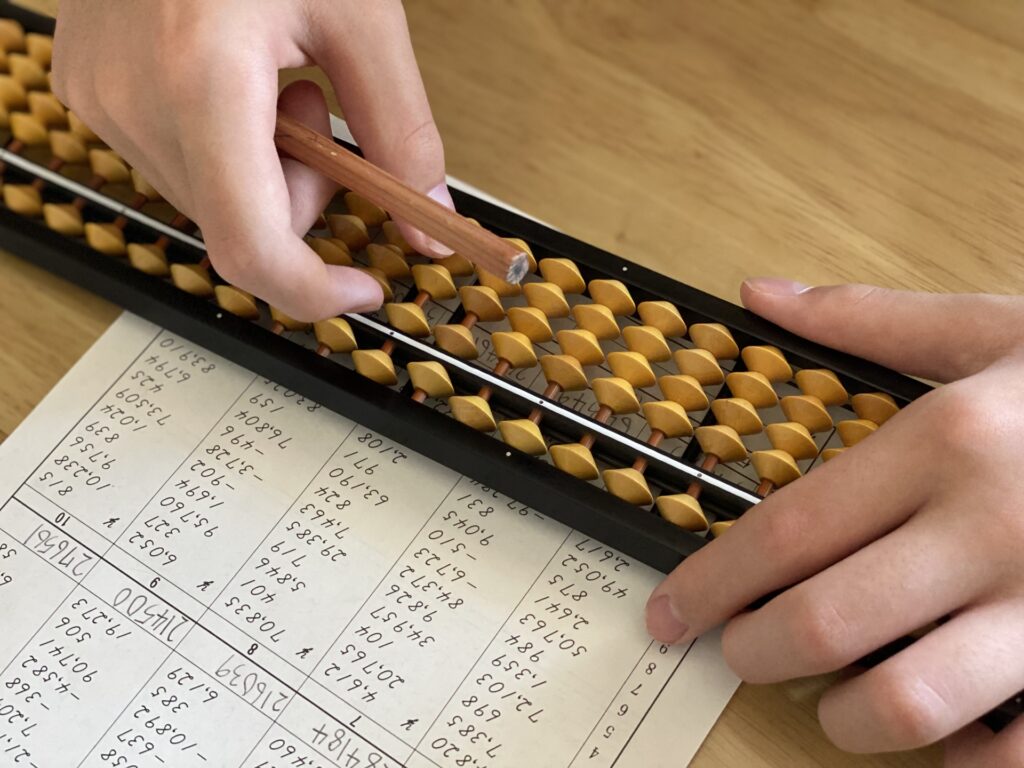
そこで5、6年前から始めたのが、たまたま足立区のセンターから依頼があった高齢者のそろばん教室だ。月2回、区のセンターで行なっているが、最初は20人前後しかいなかったのが、今では30人以上の受講者がいる。
午前中に開催しているから、来る人はほとんどが年配の方ね。彼らの年代は学校で全員そろばんを習っていた時代だったから、もう一回学び直そうって人がほとんど。計算とか指を動かすことは脳トレにもなるしね
大人は子供と違い、つきっきりで指導すると恥ずかしがる。だから間違えやすい例題を前で解説したりして、直接間違えを指摘しないという。最初は子供との教え方とどのように変えればいいのか試行錯誤したそうだ。
子供にせよ大人にせよ、そろばんを通して人間関係やコミュニケーションを大切にするという考え方は同じ。
今日も先生は元気に生徒を教えている。
(インタビュー・執筆:沼邊 国太)
(編集:山之内 紅葉)